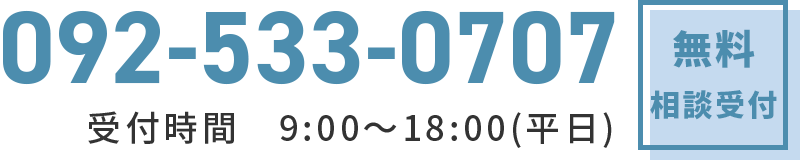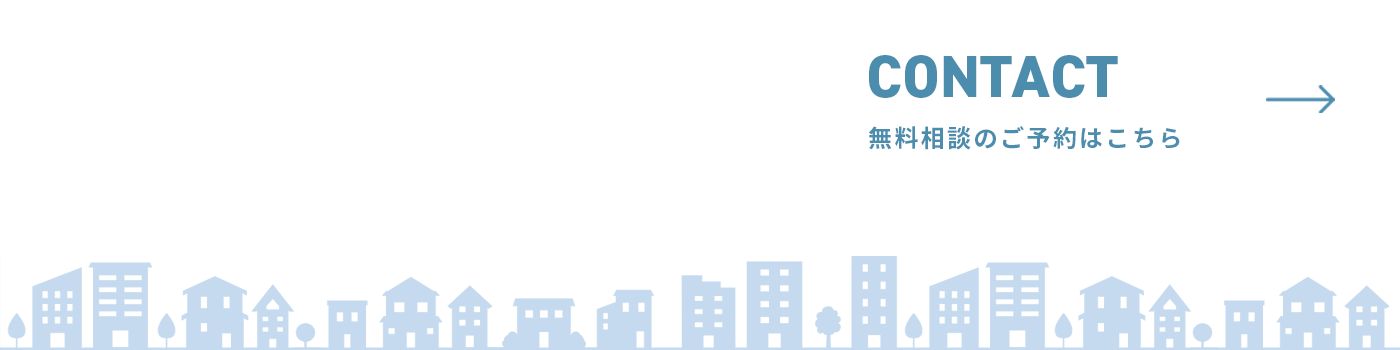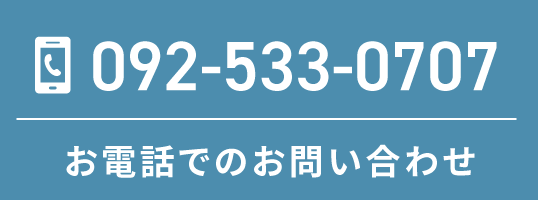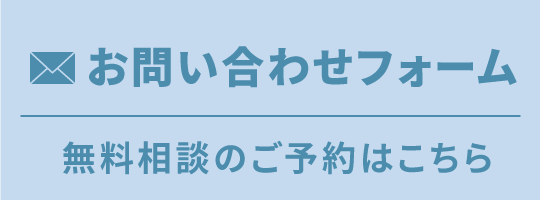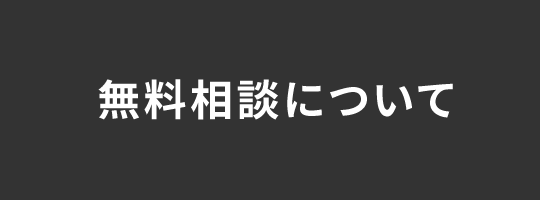企業の会計・経理業務に大きな影響を及ぼす「電子帳簿保存法」の改正。令和4年1月1日より適用された新制度は、保存要件の緩和とともに、一部では規制強化もなされ、あらゆる事業者に影響が及んでいます。
特に電子取引に関する書面保存の原則廃止は、すべての法人・個人事業主にとって無視できない変化です。
本記事では、電子帳簿保存法の3区分と改正の要点を整理し、顧問税理士として求められる実務対応や顧問先への助言の在り方について解説します。
このページの目次
1. 電子帳簿保存法の3つの保存区分とは?
電子帳簿保存法では、国税関係書類を「電子的に保存」する方法として、次の3つに区分されています。
(1)電子帳簿等保存
会計ソフト等で作成された帳簿書類(総勘定元帳や決算書など)を、紙に出力せずデータのまま保存する方法。
(2)スキャナ保存
領収書や請求書など、紙で受け取った証憑をスキャンし、画像データとして保存する方法。
(3)電子取引
請求書などをPDFで受け取ったり、ECサイトでの購入履歴など電子的な方法で完結する取引を、電子データで保存する方法。
2. 改正によってどう変わった?6つの注目ポイント
① 事前承認制度の廃止
これまで必要だった「電子帳簿等保存」や「スキャナ保存」の税務署長の承認が不要に。制度を導入したいときに、速やかに運用を開始できるようになりました。
② タイムスタンプ要件の緩和
従来の「3営業日以内」などの厳しい期限が、「2ヵ月+7営業日以内」へ緩和。さらに、訂正・削除ログが取れるシステムを使っていれば、タイムスタンプすら不要に。
③ 検索要件の緩和
「取引年月日・金額・取引先」の3項目のみの検索になりました。売上高1,000万円以下の小規模事業者であれば、検索要件自体が不要になるケースも。
④ スキャナ保存後の原本廃棄が可能に
「適正事務処理要件」が撤廃され、正しくスキャンされていることを確認すればすぐに紙を廃棄できるようになり、ペーパーレス化が一気に進みます。
⑤ 電子取引の書面保存は原則禁止に
PDFやECサイトの履歴などで受領したデータは、必ず電子で保存しなければなりません。データ保存を行う場合には、タイムスタンプ付与あるいは削除・訂正のログが確認できる会計ソフトや検索機能を有するシステムへの保存が求められます。
これらのシステムが用意できない場合には、訂正や防止に関する事務処理規程の作成及びファイル名の入力や、エクセルなどによる一覧表の作成によって検索要件を満たすことも可能です。
⑥ 不正への罰則強化
改ざんや隠蔽があった場合には、通常の重加算税に加え、さらに10%の加重課税がされるという厳しい措置が導入されました。
3. 顧問税理士としての役割と対応ポイント
電子保存導入支援の全体像
顧問先が電子帳簿保存法に対応するためには、次の5ステップを支援する必要があります。
1. 目的と課題の明確化
単なる制度対応でなく、業務効率化・生産性向上・コスト削減といった目的を共有。
2. 対象書類の洗い出し
請求書・領収書・決算関係書類など、業務フローに応じた書類の選定。
3. 業務フローの見直し
経費精算や証憑管理の手順をスキャナ保存に対応できるよう再構築。
4. システムの選定
タイムスタンプ機能や訂正ログ、検索機能など要件を満たすクラウドシステムを推奨。
5. 従業員への周知と運用体制の整備
実務担当者がスムーズに対応できる体制づくりも支援。
4. 顧問先に伝えるべき「義務」と「メリット」
義務:すべての事業者に影響する電子取引保存
電子取引(PDFでの請求書授受、ネット通販、クラウド請求書発行など)を行っている事業者は、例外なく電子保存が義務化されました。
紙への出力では対応不可となるため、早急な体制整備が求められます。
メリット:コスト削減・生産性向上・業務効率化
要件が緩和されたことで、電子帳簿保存は一層導入しやすくなりました。保管スペース・印刷代・ファイリング作業などの削減により、経理業務の効率化が実現します。
加えて、テレワークとの親和性が高く、働き方改革にもつながる点は大きな魅力です。
まとめ
電子帳簿保存法は、デジタル時代において不可欠な法制度であり、その遵守はビジネスにおける効率性と法令遵守を兼ね備える鍵です。税理士のサポートを受けることで、電子帳簿保存法の実効性はさらに向上し、スムーズなデジタル移行が可能となります。
これから電子帳簿保存の導入を考えている方は、専門家の助言を積極的に取り入れ、最適なソリューションを実現してください。